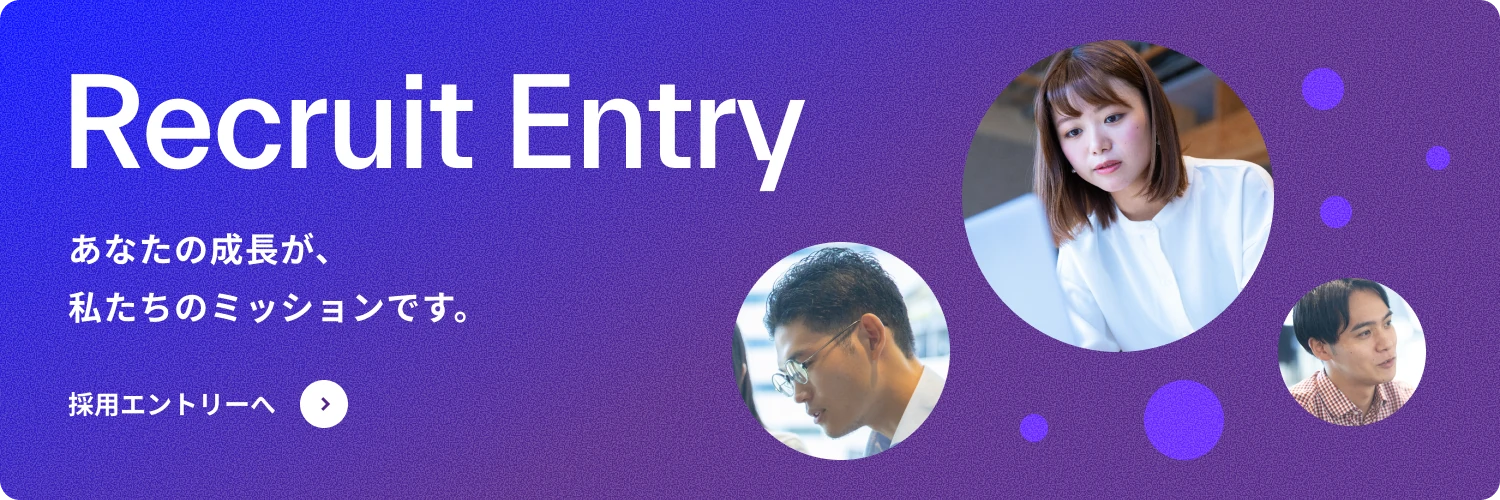WebGPUって結局何なのか
WebGPUは、WebブラウザからDirect3D 12やMetal、VulkanといったモダンなグラフィックスAPIを抽象化して扱えるようにした低レベルAPIです。W3Cの「GPU for the Web」Working Groupが2017年頃から約6年をかけて仕様策定を進めてきた成果物で、Apple、Google、Intel、Microsoft、Mozillaといった主要ベンダーが参加しています。
WebGLとの違いを一言で表すなら、「GPUをより本気で使えるようになった」という感じでしょうか。WebGLはOpenGL ES 2.0/3.0をベースにしているのに対し、WebGPUはより現代的なGPU APIの設計思想を取り入れています。具体的には、明示的なリソース管理、コマンドバッファモデル、そして汎用GPU計算(GPGPU)の一級サポートといった特徴があります。

5つの変化ポイント
自分がこの技術を触ってみて特に重要だと感じたポイントを挙げてみます。
1. GPGPUがWebで本格的に使える
WebGLでもシェーダーを駆使すればGPU計算は可能でしたが、あくまで「レンダリングの副産物」としての利用でした。WebGPUではcomputeパイプラインが正式にサポートされ、ストレージバッファやストレージテクスチャを通じて高スループットのデータ並列計算を素直に記述できます。
Chromeチームの報告によると、機械学習モデル推論において、WebGLベースの実装と比較して3倍以上の速度向上が得られるケースがあるとのこと。ブラウザ内でのAI処理がより現実的になってきたという実感があります。
2. ドローコールのオーバーヘッドが大幅に削減
WebGLでは、描画のたびにJavaScriptからAPIを呼び出す必要があり、大規模なシーンでCPUがボトルネックになりがちでした。WebGPUではGPUCommandEncoderでコマンドを事前にエンコードし、GPUCommandBufferとしてまとめてGPUQueueにサブミットする方式を採用しています。
これにより、大量のオブジェクトを描画する際のCPU負荷を大きく抑えられます。マルチパスレンダリングや複雑なシーン構成でも、より安定したフレームレートを維持しやすくなりました。
3. シェーダー言語がWGSLに統一
WebGPU専用のシェーディング言語としてWGSL(WebGPU Shading Language)が設計されました。GLSLとはだいぶ書き味が異なりますが、TypeScriptに慣れている人であればそれほど違和感なく書けると思います。
GPUShaderModuleを作成する際にはWGSLソースをコンパイルするわけですが、GPUCompilationInfo/GPUCompilationMessageといったインターフェースを通じてコンパイル時の警告やエラーを詳細に取得できるようになっています。デバッグ体験がWebGL時代より格段に向上しました。
4. リソース管理が明示的になった
GPUBufferやGPUTextureといったリソースは、作成時にUsageフラグ(VERTEX、INDEX、UNIFORM、STORAGE、COPY_SRC、COPY_DSTなど)を指定します。これによってドライバ側がリソース配置や同期を最適化できるようになっています。
最初は「面倒くさいな」と思ったのですが、実際に使ってみるとリソースの使い方が明確になり、むしろバグを減らせる印象です。Chromium実装では、テクスチャコンポーネントのスウィズル機能も追加されており、色成分の並べ替えがシェーダー側のブラン���を減らす形で活用できます。
5. セキュリティモデルがWebに適合
ネイティブのD3D12やVulkanと同等のパフォーマンスを狙いながら、Webのセキュリティモデルに適合させているのがWebGPUの面白いところです。Secure Contextのみで利用可能で、GPUアクセスはブラウザプロセスのサンドボックス内に隔離されています。
out-of-boundsアクセスの定義やリソース初期化の要件など、未定義動作による情報漏洩を避ける設計がなされています。業務アプリケーションでGPU計算を活用する際も、セキュリティ面で安心感があります。
各ブラウザの対応状況
主要ブラウザの現状を整理しておきます。
Chromeはバージョン113でデスクトップ向けにWebGPUをデフォルト有効で出荷しており、Windows(Direct3D 12対応)、macOS、VulkanサポートのChromeOSデバイスが対象です。Android向けはChrome 121(2024年1月17日リリース)からAndroid 12以上かつQualcomm/ARM GPUを搭載した端末で利用可能になりました。
FirefoxもWebGPUを正式サポートしており、EdgeはChromium系なのでChromeと同様の対応状況です。
Safari 26でついにApple各OSでもWebGPUが利用可能になり、iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、visionOS 26で動作します。実測ベンチマークでは、Safari 26のWebGPUバックエンドはWebGLと比較して約35%高速という報告もあります。
ただし、Safari 26.1/26.2では、SVG画像を扱うGPUQueue.copyExternalImageToTextureの不具合やWebCodecsとWebGPUを連携した動画再生で黒画面になる問題などが修正されています。まだ細かいエッジケースでの問題は出てくる段階なので、本番投入時は十分なテストが必要でしょう。
実務での活用シナリオ
自分が考える実務での活用シナリオをいくつか挙げてみます。
データビジュアライゼーションの分野では、大量のデータポイントをリアルタイムに描画するダッシュボードで威力を発揮しそうです。従来はSVGやCanvasでパフォーマンスの限界に悩まされることが多かったですが、WebGPUを使えばより高密度な可視化が可能になります。
機械学習の推論もブラウザ内で完結できるようになってきています。TensorFlow.jsがWebGPUバックエンドをサポートしており、クライアントサイドでのAI処理が現実的になりました。サーバーにデータを送らずに処理できるのは、プライバシーの観点でも魅力的です。ただし、Safari 26でのTensorFlow.js + WebGPU利用時に勾配が0になる問題なども報告されているので、フレームワークとブラウザ実装の整合性には注意が必要です。
ゲームや3Dコンテンツについては、AAAクラスの3Dレンダリングがブラウザで実現できるようになります。Compute-based particlesやポストエフェクトなど、これまでネイティブアプリでしかできなかった表現がWebで可能になるのはワクワクします。
Transfer ManagerとCRTの活用
大容量のテクスチャやメッシュデータを扱う場合は、効率的なデータ転送が重要になってきます。byte-rangeリクエストの自動活用や水平スケールといった最適化は、WebGPUアプリケーションのパフォーマンスを左右する要素です。
GPUへのリソースアップロードを適切に管理しないと、フレーム落ちの原因になりがちです。非同期でのリソース準備と、レンダリングループの分離を意識した設計が必要になるでしょう。
開発環境のセットアップ
実際に���してみる場合の環境構築について触れておきます。
まずnavigator.gpuの存在確認から始めます。GPUインターフェースを取得したら、requestAdapter()でGPUAdapterを取得し、さらにrequestDevice()でGPUDeviceを取得するのが基本的な流れです。
GPUAdapterからは利用可能な機能フラグ(features)やリソース上限(limits)、ベンダー・デバイス情報を含むGPUAdapterInfoを取得できます。開発時は、対象とするデバイスのcapabilitiesに合わせてフィーチャーを選択することになります。
TypeScript向けには@webgpu/typesパッケージが用意されているので、型補完の恩恵を受けながら開発できます。Three.jsもWebGPUバックエンドを実験的にサポートしているので、既存のThree.jsプロジェクトからの移行も選択肢になりそうです。
これからWebGPUを始めるなら
MDNが公式リファレンスとして、GPU/GPUAdapter/GPUDevice/GPURenderPipeline/GPUComputePipeline/GPUBuffer/GPUTextureなど主要インターフェースの詳細な仕様やサンプルコードを提供しています。まずはそこから始めるのがいいでしょう。
Chrome for DevelopersのWebGPU概要ドキュメントでは、最小限の描画例から複数パイプラインを用いたシーン構成、Computeパスの組み込みまで解説されているので、段階的に学習を進められます。
Android開発者向けには、Jetpackのandroidx.webgpuライブラリが用意されており、Kotlinからもモダンなグラフィックスプログラミングが可能です。ブラウザ外も含めた広義のWebGPUエコシステムが拡大しているのを感じます。
主要ブラウザでの対応が完了した今、WebGPUはフロントエンドエンジニアにとって習得しておくべき技術の一つになったと言えます。GPUプログラミングの経験がなくても、JavaScriptの非同期処理やPromiseベースのAPIに慣れていれば、WebGPUの学習曲線はそれほど急ではありません。ぜひ一度触ってみてください。