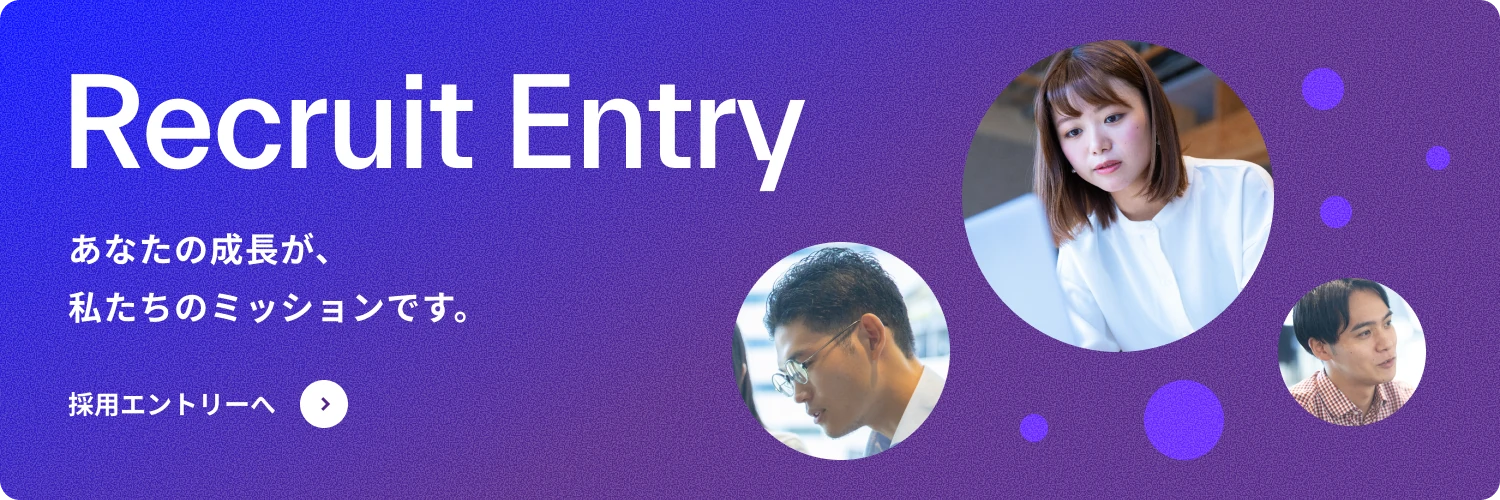AWS AppSync hydrated() 関数の真実と2025年における最適な実装戦略
hydrated() 関数の本当の役割を理解する
オフライン機能と密接に結びついた初期化プロセス
AWSAppSyncClient.hydrated() は、単なる初期化待ちのPromiseではありません。この関数は「AppSync JavaScript SDK v2」において、オフラインキャッシュの「リハイドレーション」が完了するまで待機するための仕組みです。
AppSyncSDKのソースコードを詳しく見てみると、以下のような実装になっています。
private hydratedPromise: Promise<AWSAppSyncClient<TCacheShape>>;
hydrated() {
return this.hydratedPromise;
}
// コンストラクタ内での初期化
this.hydratedPromise = disableOffline
? Promise.resolve(this)
: new Promise(resolve => {
resolveClient = resolve;
});ここで重要なのは disableOffline パラメータの存在です。オフライン機能が有効な場合、AppSyncクライアントは「永続化されたキャッシュデータ」をIndexedDBやLocalStorageから読み込み、Apollo Cacheを再構築します。この処理が完了するまで、GraphQLオペレーションを安全に実行できません。
React環境における Rehydrated コンポーネント
React環境では、<Rehydrated> コンポーネントを使用して、より宣言的にこの初期化プロセスを扱うことができました。
import { Rehydrated } from 'aws-appsync-react';
const App = () => (
<AWSAppSyncProvider client={client}>
<Rehydrated>
{/* キャッシュの再水和が完了後にレンダリング */}
<MainApplication />
</Rehydrated>
</AWSAppSyncProvider>
);このパターンにより、アプリケーション起動時にオフラインデータが存在する場合でも、適切にデータを復元してからUIを描画できる仕組みでした。
2025年における重大な転換点
AppSync SDK v2のメンテナンス終了という現実
AWS公式のアナウンスによると、AppSync JavaScript SDK v2は「2024年6月30日」をもってメンテナンスモードに移行しました。これは以下を意味します。
- 新機能の追加は一切行われない
- セキュリティパッチ以外の更新は基本的に停止
- 互換性の問題が発生しても修正される保証がない
現在も動作はしますが、技術的負債として蓄積される前に、早急な移行計画を立てる必要があります。
AWSが推奨する2つの移行パス
AWS公式ドキュメントでは、明確に2つの移行パスが示されています。
移行パス1:Amplify v6 GraphQLクライアントへの移行(推奨)
Amplifyチームが開発する新しいGraphQLクライアントは、AppSyncとの統合を前提に設計されています。型安全性の向上、リアルタイムサブスクリプションの改善、そして何よりも継続的なサポートが約束されています。
import { generateClient } from 'aws-amplify/api';
import { createTodo } from './graphql/mutations';
const client = generateClient();
// hydrated()の呼び出しは不要
const result = await client.graphql({
query: createTodo,
variables: {
input: {
name: "新しいタスク",
description: "Amplify v6での実装"
}
}
});移行パス2:Apollo Client v3 + AppSync用リンクの組み合わせ
既存のApolloエコシステムを活用したい場合は、Apollo Client v3と専用のAppSyncリンクを組み合わせる選択肢があります。
import { ApolloClient, InMemoryCache, createHttpLink } from '@apollo/client';
import { createAuthLink } from 'aws-appsync-auth-link';
import { createSubscriptionHandshakeLink } from 'aws-appsync-subscription-link';
const httpLink = createHttpLink({
uri: '<https://xxxxx.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphql>'
});
const authLink = createAuthLink({
url: '<https://xxxxx.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphql>',
region: 'ap-northeast-1',
auth: {
type: 'API_KEY',
apiKey: 'da2-xxxxxxxxxxxxxxxxx'
}
});
const client = new ApolloClient({
link: authLink.concat(httpLink),
cache: new InMemoryCache()
});
// hydrated()は存在しない、即座に使用可能ただし、重要な制限事項があります。v3系のAppSyncリンクは「オフライン機能を提供しない」ことが公式READMEで明記されています。
hydrated()が必要なケースと不要なケースの見極め
まだhydrated()が必要なケース
以下の条件をすべて満たす場合、hydrated()の使用が必要です。
- レガシーなAppSync JavaScript SDK v2を使用している
- オフライン機能を有効にしている(disableOffline: falseまたは未指定)
- SPAやReact Nativeなどのクライアントサイドアプリケーション
このような環境では、アプリケーション起動時に以下のような実装が必要です。
const client = new AWSAppSyncClient({
url: '<https://xxxxx.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphql>',
region: 'ap-northeast-1',
auth: {
type: 'AWS_IAM',
credentials: () => Auth.currentCredentials()
},
offlineConfig: {
keyPrefix: 'myapp-',
}
});
// オフラインキャッシュの初期化を待つ
await client.hydrated();
// ここから安全にGraphQLオペレーションを実行
const result = await client.query({
query: gql`
query GetTodo($id: ID!) {
getTodo(id: $id) {
id
name
description
}
}
`,
variables: { id: 'todo-1' }
});hydrated()が不要なケース
以下のいずれかに該当する場合、hydrated()は不要です。
Amplify v6を使用する場合(推奨)
最新のAmplifyドキュメントに従って実装すれば、hydrated()の概念自体が存在しません。
Apollo Client v3 + AppSyncリンクを使用する場合
オフライン機能が提供されないため、初期化待ちの必要がありません。
サーバーサイド(Node.js/Lambda)から実行する場合
公式のサーバーサイド実装ガイドによると、サーバー環境ではオフラインキャッシュの概念が存在しないため、hydrated()は不要です。
// Lambda関数での実装例
import { Amplify } from 'aws-amplify';
import { generateClient } from 'aws-amplify/api';
import { listTodos } from './graphql/queries';
Amplify.configure({
API: {
GraphQL: {
endpoint: process.env.GRAPHQL_ENDPOINT,
region: process.env.AWS_REGION,
defaultAuthMode: 'iam',
}
}
});
export const handler = async (event) => {
const client = generateClient();
// hydrated()は不要、即座にクエリ実行可能
const result = await client.graphql({
query: listTodos,
authMode: 'iam'
});
return {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify(result.data)
};
};認可方式の最新動向と実装パターン
AppSyncがサポートする5つの認可モード
AppSyncの公式ドキュメントによると、2025年現在、以下の5つの認可モードがサポートされています。
表 AppSyncの認可モード比較
認可モード | 主な用途 | 有効期限 | 推奨される使用場面 |
|---|---|---|---|
API Key | パブリックAPI・開発環境 | 最大365日 | プロトタイプ開発、公開データの配信 |
AWS IAM | サーバー間通信 | IAMロールに依存 | Lambda関数、EC2インスタンスからの接続 |
Cognito User Pools | ユーザー認証が必要なアプリ | トークン有効期限に依存 | B2C/B2Bアプリケーション |
OpenID Connect | 外部IdPとの連携 | トークン有効期限に依存 | エンタープライズSSO連携 |
Lambda Authorizer | カスタム認証ロジック | Lambda関数の実装に依存 | 複雑な認可要件、レガシーシステム連携 |
各認可モードの選択は、セキュリティ要件とユースケースに応じて慎重に検討する必要があります。
Amplify v6での認可モード切り替え
Amplify v6では、クエリごとに認可モードを柔軟に切り替えることができます。
import { generateClient } from 'aws-amplify/api';
const client = generateClient();
// API Keyを使用(パブリックデータの取得)
const publicData = await client.graphql({
query: listPublicPosts,
authMode: 'apiKey'
});
// Cognitoユーザー認証を使用(プライベートデータ)
const privateData = await client.graphql({
query: getUserProfile,
authMode: 'userPool'
});
// IAM認証を使用(管理者権限が必要な操作)
const adminData = await client.graphql({
query: listAllUsers,
authMode: 'iam'
});既存プロジェクトの移行戦略
段階的移行アプローチの採用
既存のv2 SDKを使用しているプロジェクトを一気に移行するのはリスクが高いため、段階的なアプローチを推奨します。
フェーズ1:現状分析と影響範囲の特定(1-2週間)
現在のコードベースを精査し、以下の要素を特定します。
- hydrated()を呼び出している箇所のリストアップ
- オフライン機能への依存度の評価
- カスタムリゾルバーやディレクティブの使用状況
- 認証・認可フローの複雑度
フェーズ2:移行先の技術選定(1週間)
プロジェクトの要件に応じて、Amplify v6かApollo v3のどちらを選択するか決定します。
オフライン機能が必須要件の場合、以下の選択肢を検討する必要があります。
- Amplify DataStoreの採用(Conflict Resolutionも含めて評価)
- Apollo Client v3 + カスタムオフライン実装
- Progressive Web App (PWA)技術を活用した独自実装
フェーズ3:パイロット実装(2-3週間)
最もシンプルな機能から移行を開始し、以下の観点で検証を行います。
- パフォーマンスの比較測定
- エラーハンドリングの動作確認
- 認証フローの互換性確認
- 既存のテストスイートの動作確認
フェーズ4:本格移行(1-3ヶ月)
パイロット実装で得られた知見を基に、全機能の移行を進めます。この際、「Feature Flag」を活用して、問題が発生した場合に即座にロールバックできる体制を整えることが重要です。
移行時の注意点とベストプラクティス
移行作業を進める上で、以下の点に特に注意が必要です。
キャッシュポリシーの再設計
v2 SDKのオフラインキャッシュとAmplify v6やApollo v3のキャッシュ戦略は根本的に異なります。特に「DeltaSync」や「Optimistic Response」の動作が変わるため、ユーザー体験への影響を慎重に評価する必要があります。
エラーハンドリングの見直し
v2 SDKでは暗黙的に処理されていたネットワークエラーやタイムアウトが、新しいクライアントでは明示的なハンドリングが必要になる場合があります。
// Amplify v6でのエラーハンドリング例
try {
const result = await client.graphql({
query: createTodo,
variables: { input: todoInput }
});
// 成功処理
} catch (error) {
if (error.errors) {
// GraphQLエラー(バリデーションエラーなど)
error.errors.forEach(err => {
console.error(`GraphQL error: ${err.message}`);
});
} else if (error.networkError) {
// ネットワークエラー
console.error(`Network error: ${error.networkError}`);
} else {
// その他のエラー
console.error(`Unknown error: ${error}`);
}
}パフォーマンス最適化の新たな視点
バンドルサイズの削減効果
v2 SDKからAmplify v6への移行により、多くのプロジェクトで「バンドルサイズの削減」が報告されています。
表 SDKバンドルサイズ比較(gzip圧縮後)
SDK | バンドルサイズ | 備考 |
|---|---|---|
AppSync SDK v2(フル機能) | 約180KB | オフライン機能を含む |
Amplify v6(GraphQLのみ) | 約65KB | Tree-shakingにより必要な機能のみ |
Apollo v3 + AppSyncリンク | 約95KB | オフライン機能なし |
この削減効果は、特にモバイル環境でのFirst Contentful Paint (FCP)やTime to Interactive (TTI)の改善に直結します。
リアルタイムサブスクリプションの改善
Amplify v6では、WebSocketコネクションの管理が大幅に改善されており、以下のような利点があります。
- 自動再接続のロジックが強化され、ネットワーク断続時の安定性が向上
- サブスクリプションのライフサイクル管理が簡素化
- メモリリークのリスクが低減
// Amplify v6でのサブスクリプション実装
const subscription = client.graphql({
query: onCreateTodo
}).subscribe({
next: ({ data }) => {
console.log('New todo created:', data.onCreateTodo);
},
error: (error) => {
console.error('Subscription error:', error);
}
});
// クリーンアップ(コンポーネントのアンマウント時など)
subscription.unsubscribe();セキュリティ強化のための追加考慮事項
認証トークンの管理強化
2025年のセキュリティベストプラクティスに従い、以下の実装パターンを推奨します。
トークンのローテーション戦略
Amplify v6では、トークンの自動更新メカニズムが改善されています。しかし、長時間実行されるアプリケーションでは、明示的なトークンローテーション戦略が必要です。
import { fetchAuthSession } from 'aws-amplify/auth';
// トークンの有効期限をチェックして必要に応じて更新
const ensureValidToken = async () => {
const session = await fetchAuthSession();
if (session.tokens?.idToken) {
const decodedToken = session.tokens.idToken.payload;
const expirationTime = decodedToken.exp * 1000;
const currentTime = Date.now();
const timeUntilExpiry = expirationTime - currentTime;
// 有効期限が5分以内の場合、トークンを更新
if (timeUntilExpiry < 300000) {
await fetchAuthSession({ forceRefresh: true });
}
}
};GraphQLクエリの深さ制限
AppSyncでは、クエリの深さ制限(Query Depth Limiting)を設定することで、悪意のあるクエリからAPIを保護できます。移行時には、この設定を見直す良い機会です。
2025年以降を見据えた技術選定
GraphQL Federationへの対応準備
AWSはAppSyncのGraphQL Federation対応を段階的に強化しています。将来的にマイクロサービスアーキテクチャへの移行を検討している場合、Federationに対応しやすいクライアント実装を選択することが重要です。
Amplify v6は、Federation対応を前提とした設計になっているため、将来的な拡張性の観点からも有利です。
エッジコンピューティングとの統合
CloudFront FunctionsやLambda@Edgeとの統合を考慮すると、軽量なクライアント実装が有利になります。hydrated()のようなクライアントサイドの初期化処理は、エッジでの実行には適さないため、この観点からもv2 SDKからの移行は必須といえます。
実装例:v2からAmplify v6への具体的な書き換え
Before(AppSync SDK v2)
import AWSAppSyncClient from 'aws-appsync';
import { AUTH_TYPE } from 'aws-appsync/lib/link/auth-link';
const client = new AWSAppSyncClient({
url: '<https://xxxxx.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphql>',
region: 'ap-northeast-1',
auth: {
type: AUTH_TYPE.AMAZON_COGNITO_USER_POOLS,
jwtToken: async () => (await Auth.currentSession()).getIdToken().getJwtToken()
},
disableOffline: false
});
// コンポーネントでの使用
class TodoList extends React.Component {
async componentDidMount() {
await client.hydrated(); // オフライン初期化を待つ
const result = await client.query({
query: gql`
query ListTodos {
listTodos {
items {
id
name
description
}
}
}
`
});
this.setState({ todos: result.data.listTodos.items });
}
}After(Amplify v6)
import { Amplify } from 'aws-amplify';
import { generateClient } from 'aws-amplify/api';
import { listTodos } from './graphql/queries';
Amplify.configure({
API: {
GraphQL: {
endpoint: '<https://xxxxx.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphql>',
region: 'ap-northeast-1',
defaultAuthMode: 'userPool'
}
}
});
const client = generateClient();
// React Hooksでの実装
const TodoList: React.FC = () => {
const [todos, setTodos] = useState([]);
useEffect(() => {
const fetchTodos = async () => {
// hydrated()は不要、即座にクエリ実行可能
const result = await client.graphql({
query: listTodos
});
setTodos(result.data.listTodos.items);
};
fetchTodos();
}, []);
return (
// UIの実装
);
};まとめ:hydrated()の時代の終焉と新たな始まり
AWSAppSyncClient.hydrated()は、オフライン対応のWebアプリケーション開発において重要な役割を果たしてきました。しかし、技術の進化とともにその役目を終えようとしています。
2025年の今、私たちが取るべき行動は明確です。v2 SDKに依存している既存プロジェクトは、早急にAmplify v6またはApollo v3への移行計画を立てる必要があります。新規プロジェクトでは、最初からAmplify v6を採用することで、将来的な技術的負債を回避できます。
hydrated()という一見些細な関数から見えてきたのは、「フロントエンド技術の急速な進化」と「それに対応し続ける必要性」です。オフライン対応という要件一つをとっても、実装アプローチは大きく変化しています。
重要なのは、単に新しい技術に飛びつくのではなく、プロジェクトの要件と将来性を見据えた上で、適切な技術選定を行うことです。hydrated()が不要になったからといって、オフライン対応が不要になったわけではありません。むしろ、より洗練された形で実装する選択肢が増えたと捉えるべきでしょう。